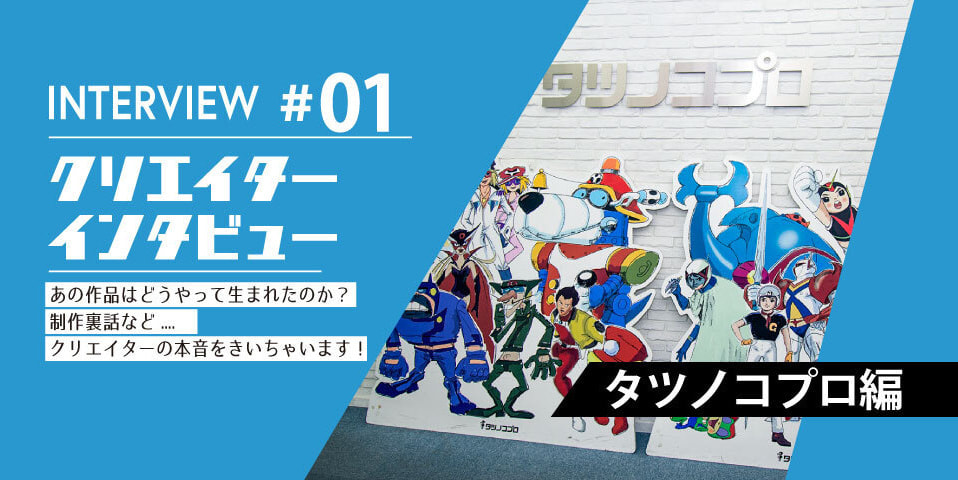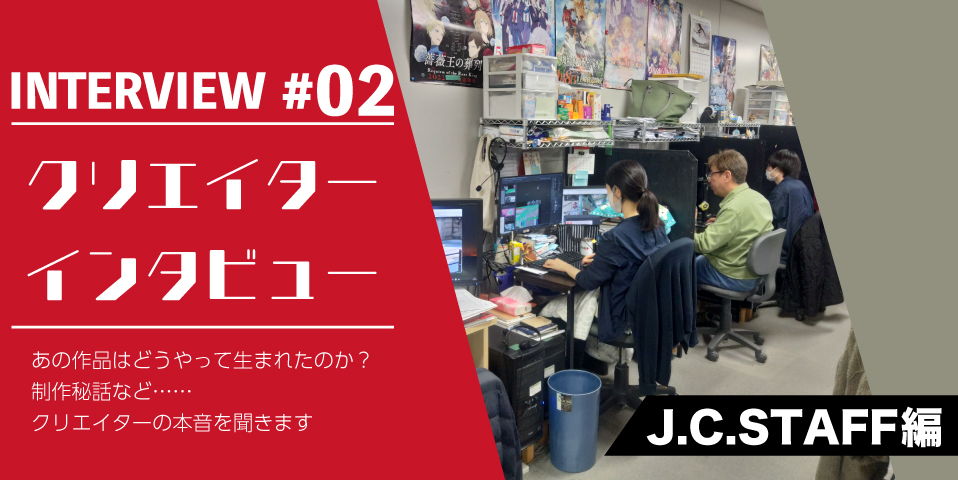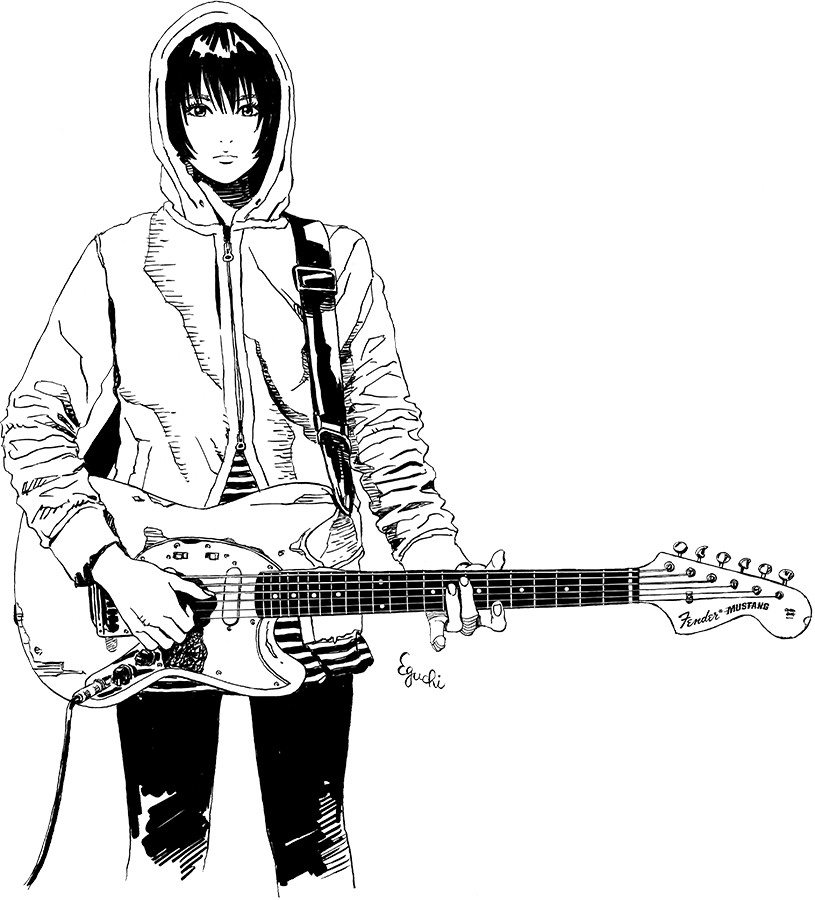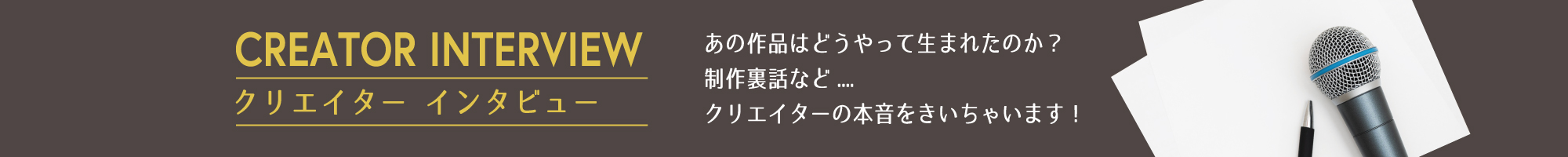
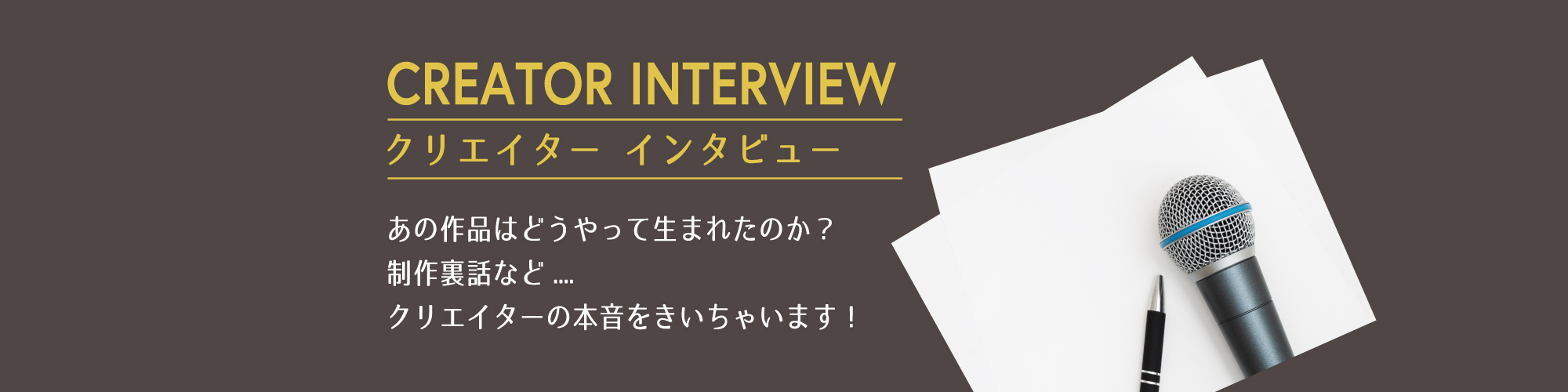
クリエイターインタビュー 第1回 前編 株式会社タツノコプロ 代表 取締役社長 伊藤響

日本を代表するアニメ制作会社はひょんなことからはじまりました。吉田は京都の生まれ。上京して挿絵や絵物語作家としてキャリアをスタートさせ、1950年代からは『パイロットエース』、『少年忍者部隊月光』などの作品を生み出し人気マンガ家として知られていました。
その吉田のもとで共に机を並べていたのが弟の吉田健二(第2代社長)と九里一平(第3代社長)です。九里の回想によれば、九里が集英社の雑誌『日の丸』に連載していた『Zボーイ』を読んだ東映動画のプロデューサーからアニメをやって貰えないかとオファーがあったのが始まりでした。
当時、三兄弟にはアニメといえばディズニーのイメージしかなかった。そこで相談したのが、当時はマンガ家として活躍していた笹川ひろしでした。笹川から「やりましょう。面白いですよ。これからはアニメの時代ですよ」という言葉を得たことで、アニメ制作の扉が開かれたのです。
もちろん、当時はアニメのノウハウはまったくないため、笹川らが練馬区大泉にあった東映動画(現東映アニメーション)で、一から学ぶことから作業は始まりました。最初に手がけた企画は、様々な事情で頓挫してしまいます。しかし、これがアニメ制作をしたいという情熱を、彼らの中で大きくしました。
そこで、それまではマンガ制作のスタジオだった竜の子プロダクションは、単独でアニメ制作に参入することを決意します。最初につくられたのが1965年に制作された『宇宙エース』です。
その制作は、まったくの手探りでした。なにしろ、アニメの知識は笹川らが数ヶ月間東映動画で学んだ内容だけ。最低限必要なセルやフィルムもどこで売っているかわからなかった。初めてのことなので、人に訊ねて売っているところを教えてもらい、手形は使えず現金払いで購入。制作資金は融資を受けました。
シナリオも最初はなかったのです。マンガの場合はコマと絵でセリフが一緒になって進む。その感覚で『宇宙エース』の際には、アフレコ用の台本もつくらず絵コンテからセリフを拾っていました。
アニメ制作においては、作業を多数が分担し、シナリオはシナリオライターが担当するといったことも、制作が進む中で学びました。『宇宙エース』では、主人公のエースがガムを食べると力が出るシーンが描かれていましたが、これはチューインガムをつくっている会社がスポンサーに入ったから。そうしたスポンサーの要望に応えることも、みんな現場での体験で得たノウハウです。
こうした柔軟な吸収力も、吉田の人間力によるものが大きかったといいます。
「創業者吉田竜夫の人間力がいろんな人を惹きつけて、タツノコならではの作風を生み出し派生して、今があるのだと思っています。とりわけ、色んな人にチャンスを与えたり、傍にあるものを吸収する力も優れた人物でした。例えば『タイムボカンシリーズ』など多くの作品でキャラクターデザインを担当した天野喜孝さんが吉田さんから”ちょっと描いてみろ”といわれた時は、まだ10代後半でした。『けろっこデメタン』も、長女のすずかさんが子供時代に描いた絵にヒントを思いついて立ち上げた企画です。吸収力というか表現力……そうしたものに長けた人だったのだと思います」
<後編はこちらから>
©タツノコプロ